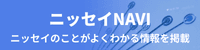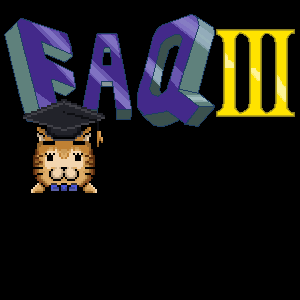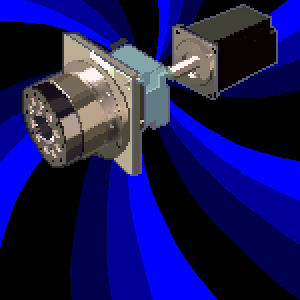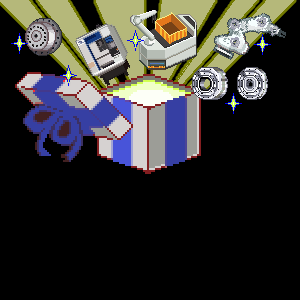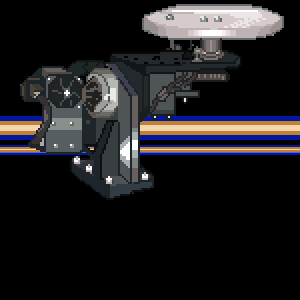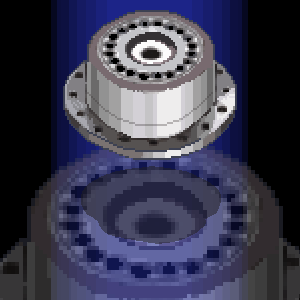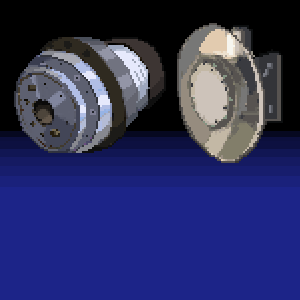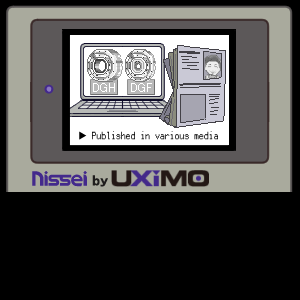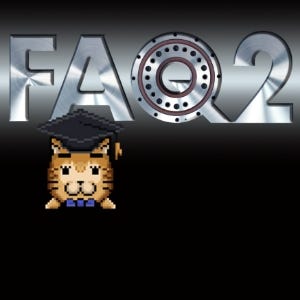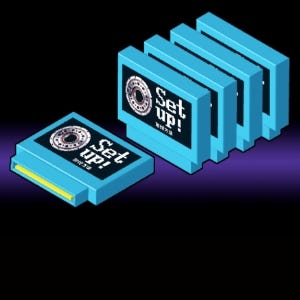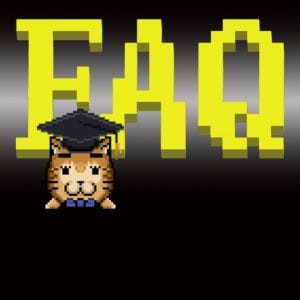高剛性減速機 製品コラム

関係者に聞いてみた!
知って得する
UXiMOインタビュー
このコーナーでは、高剛性減速機「UXiMO」の関係者が、製品の魅力などについてお答えさせていただきます。
19回目のテーマは「高剛性減速機中実タイプDGSとギアヘッドタイプの取付方法」です。
「どうやってモータを取付するの?」「どこで位置決めをするの?」「取付のイメージを教えてほしい!」といったお声をいただいておりますので、セールスエンジニアのナーリンにインタビューします。

RIN

ナーリン
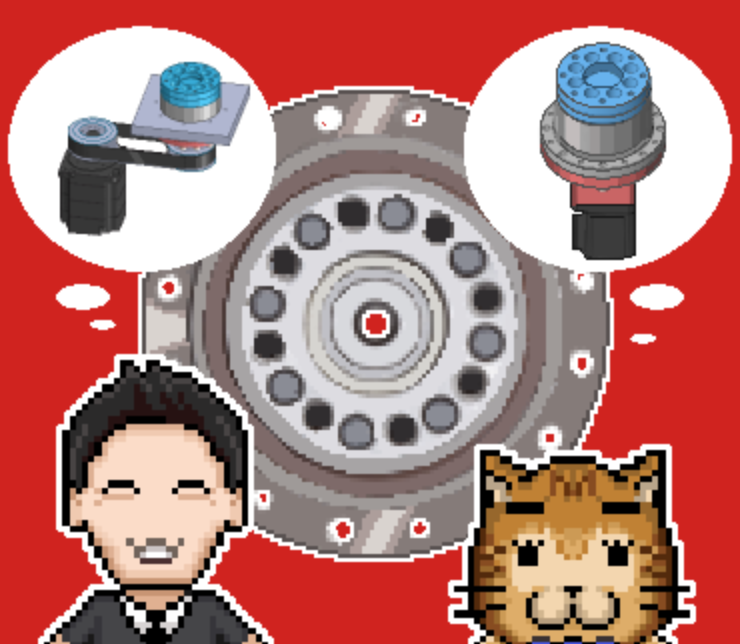
中実タイプ(DGS)の取付方法
「ナーリン、こんにちは。「高剛性減速機 中実タイプ(DGS)とギアヘッドタイプの取付方法」について、ご質問が届いております。」
「了解です。それでは「中実タイプ(DGS)の取付方法」からお話ししますね。
一般的な「タイミングベルト連結仕様」と「サーボモータ直結仕様」をご紹介します。
まずは、モータとタイミングベルトの連結です。
イラストで確認してもらった方が分かりやすいと思います。
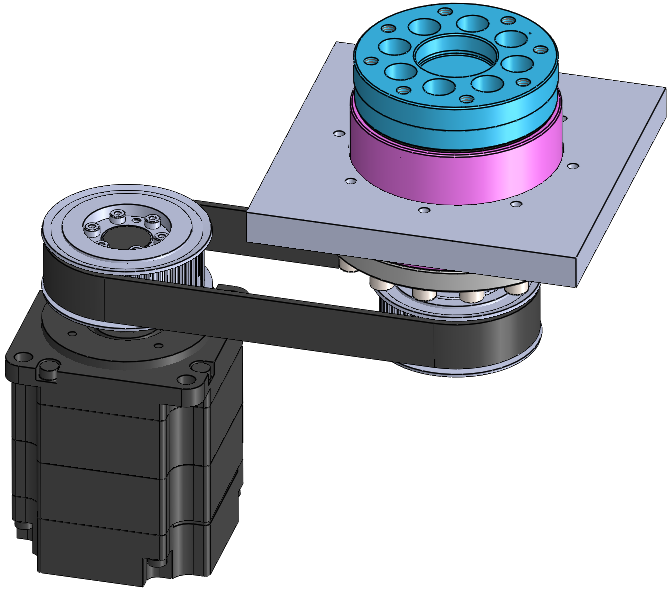
実際の動きは、中実タイプ(DGS)のデモ機で、ご紹介しております。
断面図を見てもらうともっと分かりやすいかな。」
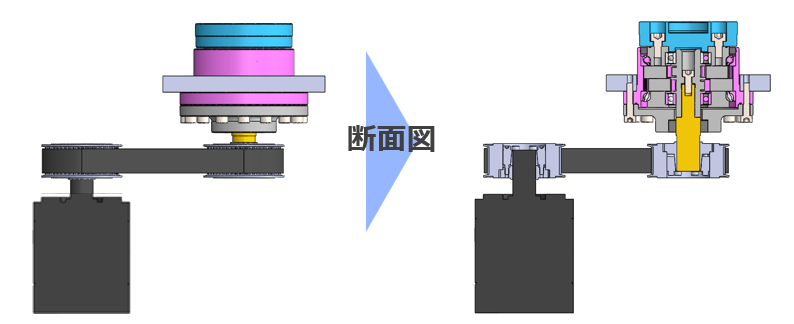
「駆動源であるモータ取付位置を離して、減速機を運転させることも可能ですね。」
「そうなんです。また、モータの取付向きを逆にすることで、軸方向にスペースを広げず、
装置へ設置することも可能です。

また、デモ機の動画では「ギア連結」も紹介していますよ。」
「減速機を固定する場合の「実際の位置決め/固定方法」はどうするのか、教えてください。」
「減速機を固定するために、通し穴を使用した場合のイメージはこんな感じです。」

通し穴使用時、お客様で取付を検討する際に“タップ(ねじ)”と“通し穴“の使い分けが可能です。
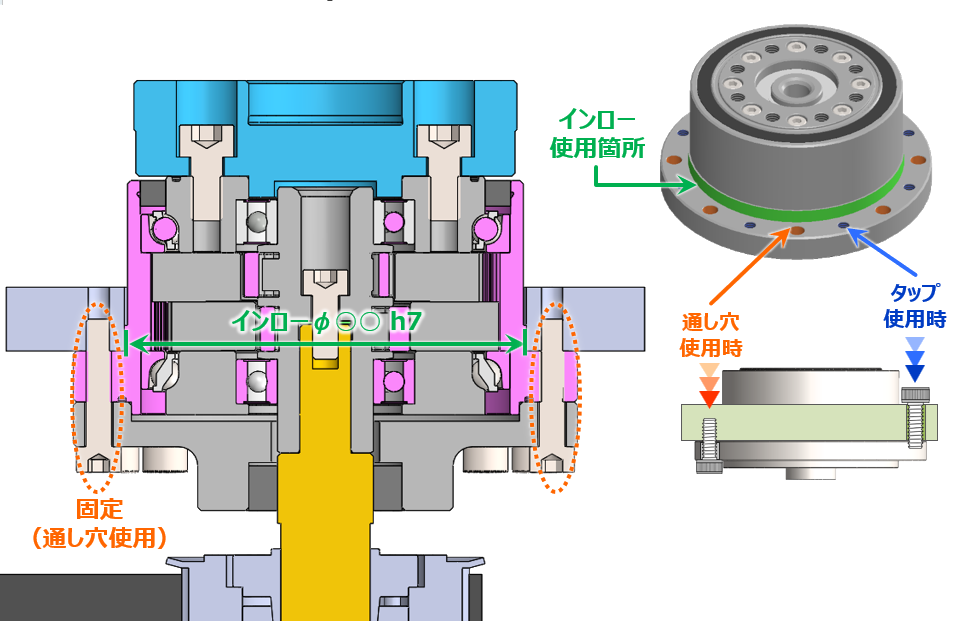
「出力部の位置決め/締結方法」は下記を参照くださいね。」
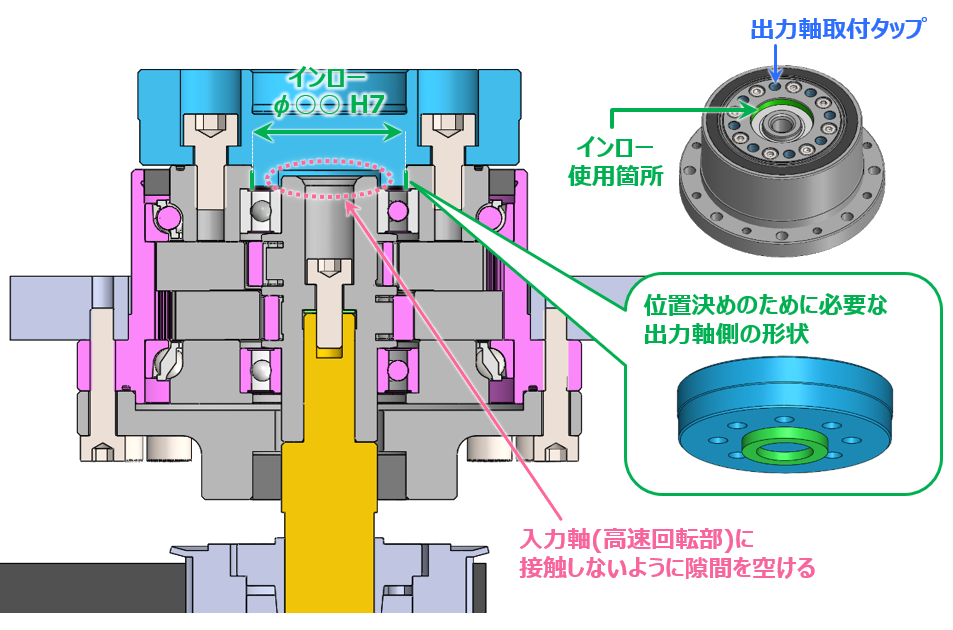
入力部の位置決め/締結方法
「次は「入力部の位置決め/締結方法」について教えてください。」
「入力部の位置決め/締結方法」は下記を参照に行ってください。」

隙間をなくすようにシム挿入などで調整が必要となりますので
ご注意くださいね!

「また、中実タイプ(DGS)は「グリス充填および密封」が必要となります。
下記のとおり、減速機の入力側、出力側の各箇所に付属のO-リングや
入力オイルシール(お客様でのご用意)を装着し、密封構造をとってくださいね。」
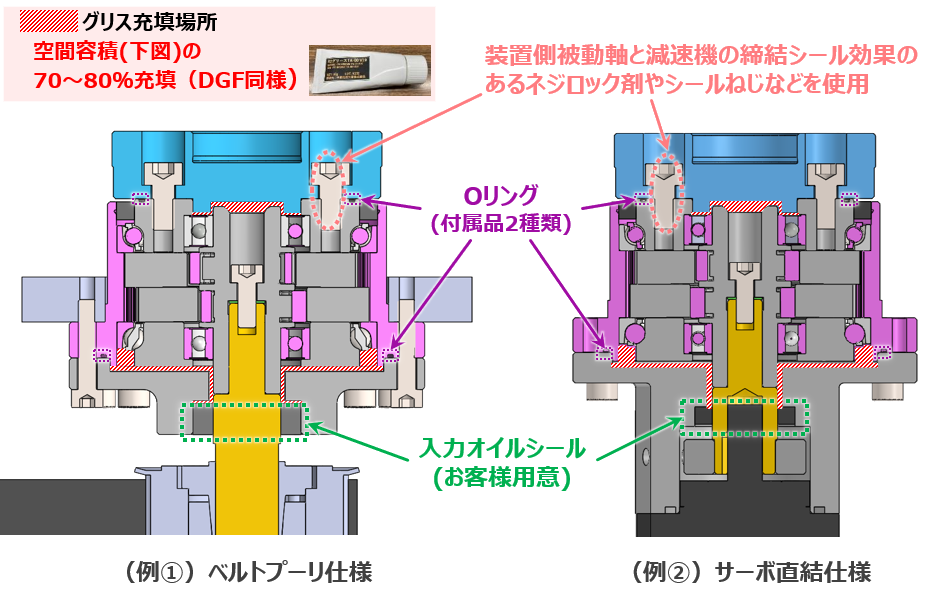
「装置側の取付イメージは下記を参考にしてくださいね。」
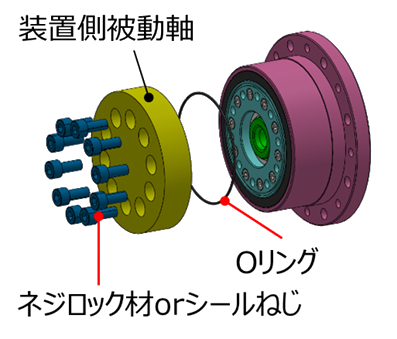
「他にも、お客様のご要望に合わせたモータブラケットでの「サーボモータ直結仕様」例をご紹介します。
後ほど紹介する「ギアヘッドタイプ」であれば、お客様にブラケットを用意してもらう必要はありませんが、例えば下記のピンク部分ブラケットを「限りなく薄くしたい」など要望がある場合は、お客様の方でブラケット・中間連結軸等をご用意いただくことで、よりコンパクトな組込みをすることが可能です。」

「中実タイプ(DGS)の詳しい取付方法のご説明ありがとうございます。
仕様用途で取付方法も変わるので、もっと知りたい!とかこんな時はどうしたらいい?
とか気になることがあればセールスエンジニアの「ナーリン」に問い合わせをお願いします。
また「大口径中空タイプ(DGH)」と「扁平・軽量タイプ(DGF)」の取付は
以下のリンク先で紹介しています。」
・大口径中空タイプ(DGH)取付方法
・扁平・軽量タイプ(DGF)取付方法
ギアヘッドタイプの取付方法
「引き続き、高剛性減速機 製品コラムの18回「ギアヘッドタイプの特長」で紹介しました
サーボモータとの連結が簡単、お客様のお手間の提言に繋がる「ギアヘッドタイプの取付方法」について教えてください。」
「はい。「ギアヘッドタイプの取付方法」は、「モータの取付」と「装置側の取付」について、
個別に説明しますね。
まず「モータの取付」です。大きく二つの工程があります。」
① サーボモータをZ-PLに取付
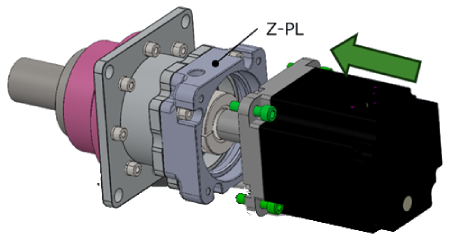
② IS軸締結ボルトを締結
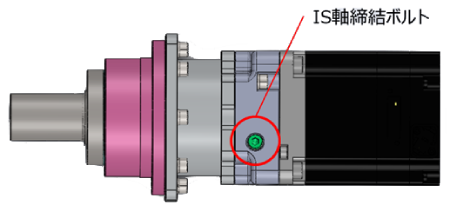

①と ②の取付順を逆にすると、モータ、減速機の軸受に大きな負荷がかかり、破損する可能性がありますので、ご注意くださいね。
「ギアヘッドタイプでは日本国内 / 海外の主要なメーカーのサーボモータを取付できます。サーボモータの仕様は変更される場合がありますので、ご発注時にはサーボモータフランジ寸法と当社減速機モータ取付部の寸法を必ず入力軸・フランジ形状詳細図でご確認くださいね。
(リンク先:2024年10月現在の代表例)
取付作業の詳細については、リンク先で詳細をご紹介しています。」
「装置側の取付、「四角形状の角フランジ」についても教えてください。」
「角フランジ!RINちゃんも製品に詳しくなってきましたね。
装置に減速機を取付する際、モータブラケット部に干渉せずにボルトが締められるよう、
通し穴を外側へ広げる目的で角フランジ形状となっています。
実際の作業は下記をご参照ください。」
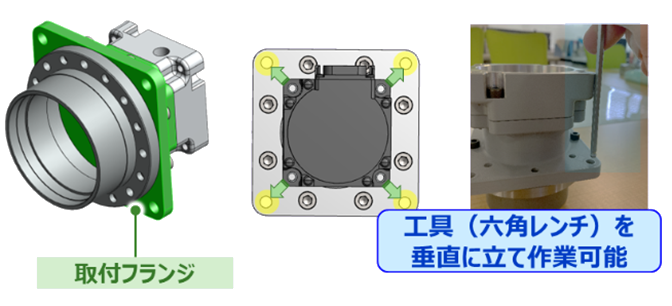
「ナーリン今回もありがとうございます。
そういえば茶ねこさんが出てこなかったな。寒いしこたつで寝ているのかな?
皆さんからのご質問がたまってきましたので、
次回は「お問い合わせ・質問スペシャル」を予定しております。
お楽しみに! バイバーイ。」